Fox hunting
彼らは息を殺し、ひっそりと、何かに脅えるように生きてきた。
国を持たないその流浪の民を、軍靴の音と共に悲劇が襲った。蹂躙したのは人間≪ニソク≫の王。薄倖の民は皆、美しい毛並みをした、獣のミミと尾を持っていた。
▼Prologue
いつの頃からか、世界には人語を解す獣≪シソク≫が現れた。
その存在が初めて確認されたのは、化石燃料の利権を争って勃発した、三回目の世界大戦の最中だった。
ある者は神の悪戯であると言い、またある者は神の領域――生命の創造や遺伝子の改良――へ手を出した人類に対する神罰であると言った。
何れにせよ、地上を支配する人類とってそれは、たとえ言語を通じ意思の疎通が図れようとも、恐怖の対象であり、排除すべき異物であった。
人類の万物の霊長たる地位を脅かすモノの出現は、それに止まらなかった。
それは丁度、前回の大戦の影を引き摺ったまま、四度目となる世界大戦の火蓋が切って落とされた頃。
人間の身体に獣の一部――翼や、ミミや、尻尾――を持ったモノが現れ始めたのだ。彼らは人間の姿をしてはいても、シソクの特徴を具えている≪混合種≫。
駆逐すべき対象とする者、人種の改良のため研究の対象として捉える者、反応は様々であった。しかし、『人類より下位のモノである』という認識だけは万人の共通するところであった。
人は言った。
『≪混合種≫は人間よりも獣に近しいモノ、≪シソク≫の一種である』、と。
そうして、混合種は言語を解す獣と共に≪シソク≫と蔑んで呼称されることとなった。
世界は最早、繰り返される大戦で減少した古き人類≪ホモ・サピエンス≫の統べるものではなく、人工的に生み出された改良人種とシソクの生きる地でもあった。
その頃には、科学と生命の倫理を冒して極めた高度な文明さえ、その終焉を迎えようとしていた。
前世紀の世界の秩序は崩壊し、各地で小国が濫立しては消えていった。新たな秩序は形を成さず、世界は混沌を極めていた。
中央大陸の北西部で彼ら――狐のミミと尾を持ったシソクの民を襲ったのは、混乱する世界が生んだ悲劇の一部だ。
人間≪ニソク≫以外を許さないその小国の王はシソクを狩り、駆逐していた。そのような王に発見されてしまったことが、美しいシソクの民の最大の不運だろう。
武器をとり立ち向かった者は死に、悲鳴を上げ逃げ惑う者は捕らえられた。
平穏な生活は一瞬にして崩壊する。それも、ただニソクの王の心一つで。
絶え間ない怒声と立ち上る黒煙のなかで、幼かった少年の心はパキリパキリと音を立てて罅割れ始めた。
▼01
足音が聞こえ、稲穂色のミミがピクリと動く。
中央大陸の北西部にある小国、ドゥエ。
その王城の奥にある牢獄のような小部屋で、彼は独りうずくまっていた。暖を取るには薄過ぎる毛布に包まっていた少年は、聞こえてきた音に反応してその身を起こした。
ところどころ裂け、破れながらも、聴覚に優れた彼のミミは、カツカツとした硬質な音が彼の部屋の前で止まったことを察知した。柵の代わりに壁と扉があるというだけのそこを、部屋とするか監獄とするかは個々人の主観によるが、中に居た彼――アイにとっては、動物を飼う檻そのものであった。
狭い檻の中で過ごす独りの時間は苦痛ではない。孤独は癒しそのものだ。
その平和を脅かす訪問者は、ガチャガチャとうるさい金属音を立てて小さな扉を開いた。
日付や時間の感覚が失われて久しいが、ここへ王の使者が訪れるのは決まって夜も更けた頃だった。
照明も窓も無い暗くじめじめとした小部屋でも、夜目の利くアイには特に問題はない。しかし、暗闇に慣れた目には薄暗い廊下の灯りすら眩しく感じる。
「出ろ。王がお呼びだ」
足音の主がそう言って顎をしゃくった。束の間の平穏が終わることを告げられても、アイの表情が変わることはない。
あぁ、自分の番がきた――そう思うだけである。
手渡された手枷を慣れた手つきで填め、重い足枷を引き摺りながらおとなしく男の後を歩いた。
(顔を殴られればいい)
『美しいだけが取柄の下等なイキモノ』を嬲り、元の顔が判らなくなるまで凌辱することに悦びを覚える王は、醜く顔を腫らしたモノを呼び出すことはない。
ドゥエの王は『下等なイキモノ』を多数、所有していた。整った造作を気の済むまで変形させ嗜虐心を満足させると、用済みになった『見苦しいモノ』は檻へと放り込み、他のコレクションを呼び出すのだ。
一人の平穏は他の一人の犠牲の上に成り立っている。それに思い至らないアイではなかったが、他者のことなど最早どうでもよかった。
(手酷く殴られてしまえばいい)
ただ生存しているだけのアイにとって、死ぬことは特に問題でもなかった。
「陛下、連れて参りました」
そう扉の向こうへ報告した男の声で到着に気付き、アイはぼんやりとした思考を止める。そしていつものように頭も心も機能を停止させた。
それは、考えることにも感じることにも疲れ果てたアイの、唯一の処世術だった。
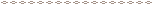
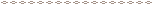
「そこを動くな」
暴力の嵐が過ぎ去った後、襤褸切れのようになったアイにそう命じて、王は慌ただしく出て行った。
いつもならば、ゴミを摘み上げるようにアイを回収して元の小部屋へと突っ込む者が現れるのに、今回はそれがない。アイがこの部屋に独り取り残されるのは初めてだ。
高級品が揃えられた部屋に美しいダガーや鞭までもが飾られているのは、ここがコレクションを愛でるためだけにあることを示している。高価な品々で飾られた、シソクを嬲るためだけの部屋。
王の気配が色濃く残るその部屋で、アイは長い金茶色の髪を乱したまま力なく床に伏せっていた。
何やら表が騒がしい――いや、騒がしいのは表だけではない。王の家臣だろうか、先程、王がここを出るまで、何人もの人がこの部屋を出入りしていた。
アイは背中の焼け付くような痛みと、聞き覚えのある音を知覚した。
(……あぁ、そうだ、これは――自分が“狩られた”時と似ている……)
分厚い扉越しのそれは、以前の記憶を呼び覚まそうとする。
(思い出してはいけない。考えてはいけない)
それが自分の身を守る最善の策だ。
アイは自分のミミをふさいでしまいたかった。しかし、腕を上げることもできない。無駄に優秀な己の聴覚をうらめしく思う。
乗馬鞭で打たれた背中は裂傷をおこしていたが、苦痛に慣れたアイにとって意識を失うほどのものではない。
かといって眠ってしまおうにも、城内の異変に気付いた彼の本能は眠りを拒否していたし、痛みが睡眠の邪魔をする。
頭までもが酷く重いのに、己の身体はそう都合よくできていないらしい。
(心地良い……)
細かなモザイク造りの硬い床は、赤く腫れあがった頬をひんやりと、優しく冷やしてくれた。
To be continued.