Fox hunting
▼02
ふいに、重々しい扉が弾かれるように開き、数人の兵士が室内に雪崩れこんだ。
王の私室≪コレクションルーム≫を制圧した兵士たちがアイを発見し、驚いたようなどよめきが僅かに上がる。扉越しに聞こえていた外の喧騒が直接、アイのミミへと届いた。
(王の軍ではない)
アイは彼らの軍服に見覚えがなかった。この国の兵は王の狩猟に同行していたから、見た覚えがないということはつまり、彼らが他国の兵だということを示していた。
(この城は他国に制圧された、のか……)
アイの身を隠すものは、彼の半身程もある大きな山吹色の尻尾と腰まで伸びた深い蜂蜜色の髪だけだったが、特に慌てることも怯えることもなかった。
一度捕らえられ、何もかもを奪われた身だ。一度も二度も同じだろう。ただ、己の生殺与奪の権利者が変わるだけのこと。自分の命も体も、どうなろうと構わなかった。
何に対しても特に反抗する意思はない。生きているからそこに存在しているだけ。死を選ばないのは、単にその決定さえ放棄していたからだ。
「悪趣味だな」
贅を尽くした煌びやかな部屋に対してか、裸で床に横たわるアイに対してか。
誰かが呼んできたのだろう、遅れてやって来た男がそう吐き捨てた。
(二角だ……)
男は白濁した半透明の二角を持っていた。
ツンツンと逆立った黒の短髪は男らしい直線的な額を露わにしており、その両端にある濁った水晶のような二角を惜しげもなく晒している。
(……それに)
監禁されて以来、見ていなかったミミや尾を持つ同胞、獣と人間の特徴を併せ持った≪混合種≫もいる。
アイを捕らえたのは人間≪ニソク≫の王であったし、王はシソクを下等生物と見做していた。シソクを相手に“狩猟”を行う程度には。
したがって、城内には純粋なニソクしかいなかったのだ。尤も、王は己以外の全てを――ニソクすらも、蔑んでいるようだったが。
片膝をついて二角の男が屈んだ。途端、目線が近くなる。鋭い視線を送る瞳で直視され、アイはそのまま見つめ返した。
遠目から見ると髪と同じく黒色をしているように思えた瞳は、こうして近くで見ると深い藍色をしていた。
(角も、瞳も)
アイは今までに見た何よりも――勿論、王の持つ宝石よりも――美しいそれに思わず見惚れた。
「≪狐≫か?」
おそらく自分のことを訊いているのだろう。この場に狐など、アイ以外にいない。
アイは二角の目を見つめたまま、頷く代わりに大きな尾をふさりと揺らして答えた。
「来るか」
目の前に手を差し出され、アイの金茶色の瞳が微かに揺らめいた。
「来るか、来ないか」
差し出した手はそのままに、二角は言葉を重ねる。
選べ、と。そう言っているような目で見つめられ、動揺する。落ち着かない。
熱で散り散りになる思考のなか、アイは殆ど無意識に手を伸ばした。
二角の手は、大きかった。
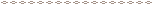
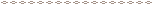
その後、アイは己の手を取った二角に担がれて、彼らの陣営へと運ばれた。
道中、二角は『見たくなければ目を瞑っていろ』と言った。しかし、目など閉じなくても、荷物のように肩へ担がれているのだ、足元くらいしか見えない。その上、時刻は深夜だ。暗闇の中でアイの五感が何かを知覚し、脳が認識しても、それは心まで届かない。
二角はおかしなことを言う――アイはそう思った。
見たくないモノは既に見終わっていた。あの日の光景以上に自分の心に何らかの影響を及ぼすモノなど、きっともう現れない。だから、今更何を視界に入れようと、どうということはない。
冷え切った心が不都合を訴えるとは思えなかった。
二角の広い肩の上で、彼の長い足が刻むリズムに揺られながら、アイの頭はのろのろと思考を巡らせていた。
王の趣味で整えられた豪奢な部屋を遠ざかるにつれ、強張った精神がゆるりと解けていく。
そのまま、アイは意識を失うようにして眠りへと落ちていった。
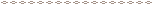
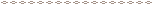
眠っていた間に怪我は手当が施されたらしい。
アイは真白い包帯で上半身をぐるぐると巻かれ、その身は硬い簡易ベッドの上にあった。
気がつけば、そこには二角ともう一人、壮年のニソクの男がいた。
戦闘向きの服を着た二角とは違って、その男はシャツの上に襟や肩、胸にキラキラとした飾りのついたジャケットを羽織っている。アイが捕らえられた日に見た、ニソクの暴君と似た格好だった。
見るからに身分の高そうな男に対し、丁寧な言葉遣いで話す二角の言葉が聞こえた。
「……だから申し上げたではありませんか。見届けるだけのことに陛下がいらっしゃることはないと」
シソクとニソクの間に争いは絶えなかったが、ここドゥエの国では、ニソクによってシソクが一方的に“駆除”されているという話があった。
『専制君主を打倒するためクーデターを起こす』――ドゥエから秘密裏にやってきた使者はこう言った。そのため、大陸の北西部にある幾つかの小国のなかで中心的な役割を果たしている、貴国ノルトヴェステンの力を借りたい、と。
その申し出を受けることにしたノルトヴェステンは監視の意味合いを込めて、少数の兵と、国王の常設私軍の長である二角を派遣したのだった。
戦をするわけではないため、国王自らドゥエに出向く必要性など皆無だったのだが、『別に危険はあるまい』と、ノルトヴェステンの王はわざわざクーデターの遂行を見届けに来ていた。
ややもすれば自ら城内の制圧に向かいそうな王を押し留めるため、二角が代わりに先陣に立って動いていたところ、アイを発見した兵に呼ばれ、ボロボロのキツネを保護するに至っていた。
「仕方あるまい。ここのところ暇だったのだ。……それに――」
二角に陛下と呼ばれた男は、途中で言葉を切ってアイを見る。
噂は本当だったのだ。青年というよりは少年に近い小柄な身体は、古いものから真新しいものまで、打撲や裂傷、火傷の痕でいっぱいだった。
「おお、目が覚めたか」
目を開け、もぞりと身じろぎしたアイに、起きたことを察した男が声をかけた。厳しさを感じさせる目元の皺も、今は安心させるように笑みの形に変えている。
このニソクも王なのか。それにしても、同じニソクの王であるのにこの国の王とは纏っている雰囲気が違いすぎる。
アイのなかでニソクの王といえば、ドゥエを治める暴君であったため、両者の違いに多少の驚きを感じていた。
王は何も言葉を返さないアイの無礼に対して怒るでもなく、ニコニコと微笑みかけてくる。
「ノルトヴェステン王、クラウス=キースベルト陛下だ」
アイに応えを促すように、二角が王の名を教える。それに対し、ノルトヴェステンの王は「構わん、構わん」と、手を振って抑えた。
「――では、青軍隊長ドノ、国へ帰るとするか」
二角との話はすでに終わっていたのだろう。齢50を過ぎても茶目っ気を忘れないクラウスは、自国の青軍隊長である二角におどけた口調でそう言い残して踵を返す。
去り際、アイに「キツネの少年よ、ゆっくりと休まれるといい」と声をかけてテントを出て行った。王の威厳溢れる顔に穏やかで親しみやすい表情を浮かべ、保護したキツネの少年に温かな頬笑みを与えるのを忘れずに。
二角は彼の仕える主を丁寧な礼で見送り、アイに向き直る。
「名は」
「……アイ」
短く問われ、アイはその名を名乗った。
名を訊かれることなど久しくなかった。ドゥエの王は下等なイキモノの持つ本来の名など気にも留めなかったため、捕らえられてからは名など無いに等しかったのだ。あのまま王の所有物であったなら、アイはその名を忘れていただろう。
(まだ大丈夫。まだ、覚えている……)
苦痛の呻きではなく、言葉を伝えるために声を発すること自体、久しぶりの行為であった。
「ロルフ=ライヒシュタインだ」
寝台に横たわるアイに、二角も簡単に自分の名を告げた。
(ロルフ)
自分の手を取ったヒトの名を、心の内で繰り返した。
To be continued.