Fox hunting
あれは、選択を迫る目だった。
『来るか』
そう言って差し出された手を取ってしまったのはなぜだったのだろう。
▼03
どのようなやり取りのもとかは定かではないが、アイの身柄はロルフの元で保護されることになったらしい。
ドゥエから僅かに西へ行ったところに、ノルトヴェステン国はあった。
ドゥエは国というよりも領邦とでもいうべき小さな国であったから、国境を挟んだところで移動にそう日数はかからない。
王の元を離れたからだろう。張りつめた糸がふつりと切れたようにこれまでの疲れがどっと押し寄せてきた。精神的にも肉体的にも疲弊していたアイは、移動中ずっと寝込んでしまった。
その間に国を越え、気がつけばノルトヴェステンへと到着していた。
アイはロルフの邸に住まい、彼の庇護下に置かれることとなった。
物心ついた頃からアイの一族は流浪を続けていたし、その後は王のコレクションとして檻へ閉じ込められていた。それゆえ、そこは彼にとって初めて体験する≪家≫であった。
まともな比較対象のないアイには、個人の住む場としてはとても広く思えた。しかし実際には、ロルフの邸は彼の持つ地位にしては至極小さく、簡素なものだったのだが。
考えて動く、ということをしないアイは、日々だらだらと無気力に過ごした。
ロルフに言われるがままに食事をし、風呂に入り、睡眠をとる。ただそれだけの生活。
ドゥエの君主が与えるのは侮蔑と嫌悪、それから凌辱と苦痛。熱にでも浮かされているかのような、快感に酔った視線と淫猥な言葉。
その手は痛みを与えるだけに存在し、温もりや保護を与えることなど有り得なかった。
ロルフはアイを拘束しないし、怪我が増えるようなこともない。無理に身体を開かれその身を穢されることも、勿論ない。
彼の手はアイの頭をワシャワシャと撫でたり、口元に食べこぼした物を拭ったりする。与えられるのは完全な安心だ。
『昼飯は自分で考えて食べろ。家にある物は何を使っても構わないし、何をしてもいい』
では、行ってくる――そう言ってロルフは仕事へと出て行く。
ロルフの生活はこうだ。日中は王宮へ行き、夕刻には邸へ戻ってアイの夕飯の世話をし、家のことを済ませる。パターン化された面白味のない生活だが、それがロルフなのだろう。
彼はアイの衣食住を世話し、特に構うこともなく、何も話さないアイと共に静かに一日を送る。
ロルフの言葉に対し、アイは僅かにミミや尾で反応を返す。この一連の遣り取りもまた、毎朝繰り返されていた。
日がな一日、日向ぼっこに勤しみ、ぼんやりと無為な日々を送るアイに向かってロルフは溜息を吐いた。
「アイ、お前昼食を摂っていないだろう」
その言葉通り、アイはロルフの留守中に食物を口にしたことはない。陽射しを含み柔らかく膨らんだ尻尾を抱いたまま、アイは答えを返した。
「考えるのはやめた」
この子供は何を言っているのだ――ロルフの顔に思案気な表情が浮かぶ。
(ロルフがそう言ったのではないか)
それも、毎朝。ロルフの表情を見て、アイは再び口を開く。
「考えて食べろと。二角が言っただろう」
アイにしては珍しい長センテンスの言葉だ。
『考えて食べろ』――たしかに彼はそう言い置いていた。自分の発言に思い至ったのか、ロルフが再度の溜息を吐いた。
「こちらへ来てからひと月は過ぎた。俺が家の中のことをやっているところをお前も見ていただろう。何も出来ない、とは言わせないぞ」
ロルフは何かをしろと言っているのだろう。では、何を。ロルフは何も命じていなかったはずだが。
疑問が態度に表れていたのか、ロルフは頭が痛いとでも言うように、二角を具えた額を抑える。そして、腹の底から息を出すように、三度目となる長い長い溜息を吐いた。
平穏な生活はアイを思考へと駆り立てる。
ロルフに対しては考えないと言っておきながら、アイの頭はその動きを止めてくれない。ドゥエに居た時はあれだけ簡単だったことなのにも関わらず。
ドゥエの王城で小さな檻に捕らわれていた時と、アイの行動自体は何ら変わらない。変わったのはその身を取り巻く環境だけだ。
それなのに――こちらへ来てからというもの、自分はどこかおかしい。まるで二年前の――仲間と、家族と共に過ごしていた頃のようだ。
暖かい窓際で日の光を浴びながら、アイは日々同じ疑問を繰り返していた。
なぜ自分は、差し出された手を取ってしまったのだろうか――
――なぜ彼は、自分を拾ったのだろうか……。
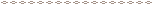
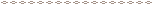
その問いはある種予感めいたモノだったのかもしれない。
その日もいつもと同じように、アイは窓際を陣取っていた。
時折聞こえる物音は二角が在宅である証拠だ。ロルフの気配に三角のミミをピクりと反応させながら、穏やかな陽射しの誘うまま、アイは夢と現の間を行き来する。
キラキラと光を反射する黄金のキツネの背に向かって、ロルフはその名を呼んだ。
「アイ」
常より僅かに硬い声音を感じ取って、アイは身体を起こした。振りかえって二角を見ると、その深い藍の瞳は真剣な色を湛えている。白濁した半透明の二角だけは変わらず、氷の結晶のようにチラチラと光を返していた。
「西の大陸国が≪狐≫であるお前を保護しようと申し出てきた」
前置きも無しに切りだされたのは、アイの処遇のことだった。思わぬ言葉に僅かに身が硬くなる。
(≪狐≫というのは保護される種だったのか……)
二年前のあの時までは人目を忍ぶようにしながらも、一族で普通に生活していたのだ。己のことではあったが、アイにとって自分がこうも大事にされる種であるとは思えなかった。
美しいから――その理由だけで希少であると定められ、保護を申し出てくる西の人間の意図などアイには知る由もなかった。ましてや、まるでペットのように愛玩される同胞の存在も、研究動物のように体を切り刻まれる存在がいることも。
そのまま、二角は話を続けた。
「どうするか、しばらく考えろ」
(考えろ、か……)
ロルフは口癖のようにその言葉を口にする。そして、二角はいつかと同じように言葉を重ねた。
「考えろ、そして選べ。お前が、自分で」
『来るか』と問うたのは二角だ。そして自分はその手を取った。
きっと、その時に全ては決まっていた。
なぜ自分は差し出された手を取ってしまったのか――いつもの問いに結論が出る。
「おれはここにいては迷惑か?」
「迷惑ではない。だが、お前はもう幼い子供のように全ての決定を保護者に任せるような年ではない。庇護されるだけの年齢でもないだろう」
アイの問いに二角が答える。
「ここにいても構わない。西大陸へ渡りたいというのならそれもいいだろう。お前の意思は誰にも縛られていない。だから選べ、自分の生き方を」
ならば――もう答えは決まっていた。後はそれを伝えるだけだ。
「では、ここに居る。二角の傍は、心地が良い」
性急過ぎる答えに、ロルフの顔に些か戸惑いが浮かぶ。それを察し、アイは言葉を付け足す。
「考えろ、と。そう言ったのは二角だろう。だからこちらで考えることにした」
アイの意思表示に対し、ロルフは「そうか」、とだけ呟く。その声音や表情からは何も窺えないが、先程の戸惑いはもう無い。
「では」
ニヤリと笑ってロルフが言った。
「俺のことを二角と呼ぶのは止めろ」
二角がこのような人の悪い笑みを浮かべるのを見るのは初めてだ。そもそも、この二角は言葉も少なければ笑顔というものも少ない。そこだけはアイと共通している。
アイは意味が分からず首を傾げた。
「お前は二角ではないのか?」
「二角だな。だが、俺はお前に名前を教えただろう?」
(あぁ)
そういうことか。ようやく合点がいった。名前で呼べと、そう言っているのだ。
「……ロルフ」
何度も胸中で呟いていた三文字をこの時初めて唇に乗せた。
わしゃわしゃと頭を撫でるのは、『よくできました』、の意。
ロルフの満足そうな笑顔を見て、アイの端っこがカチリと音を立てた。
何重にもかけていた心の鍵が開く音。
凍っていた心が溶け始めた音。
止まっていた心の時計が動き始めた音。
知らず、顔の表情筋が緩み始めた。
何を見て驚いたのか。ロルフは一瞬瞠目した。
「アイ」
穏やかな陽光を浴びて、小さな花がそろりと、その薄い花弁を開くように。
蜂蜜色のキツネの少年は、二角の男の傍らでふんわりと笑っていた。
End