Honey colored
▼01
北西の辺境にある貧しい小国とは思えぬほど、ドゥエの王の居宮は煌びやかな物品で溢れていた。
遠い東国の意匠が凝らされた器、南国の金で飾られた窓枠、北国の獣皮に西国の薄絹。極めつけが、モザイク造りの床に横たわる混合種の少年。
初めは、意識がないのかと思った。なぜなら、黄金色のその生き物は、何一つ身に着けず、逃げるでも怯えるでもなく、ただ、そこに居たから。
暴君に仕える者も、後宮という檻に入れられていた者も、皆、異変を察知するとすぐに逃げ出した。前者は他国の兵を恐れて。後者はこの機に乗じて。
そもそも、これはこの国のクーデターだ。二角の国、ノルトヴェステンはそれに手を貸したにすぎない。政変に伴い王の権力は失墜した。民意をなくした王へ従う者などいない。
王の蒐集した高価な品は根こそぎ持って行かれたのだろう、居宮深部のこの部屋以外はガランとしたもので、人も物も消え失せていた。だからこそ、この空間の異質さは目につき、『悪趣味』の一言に尽きた。
二角の声に反応したのか、少年はゆっくりと顔を上げた。
(意識はあるのか)
見た感じ、年の頃は16、7だろうか。
二角は混合種の少年を不用意に怯えさせないよう、膝をつき、高い位置にあった目線を下げた。
「≪狐≫か?」
尋ねると太い尾を揺らす。彼の身の丈の半分ほどもある、大きなそれは彼が混合種である何よりの証拠だった。
その上、キツネ――先日の下らない国際会議で保護種に指定されている。
混乱期を迎えたこの世で、既に有名無実と化している国際会議≪ラウンド≫。
西の大陸を治める大国が主宰するそれにおいて、その美しさと希少さから定められる、実に馬鹿馬鹿しい括り。保護の名の下に何をされるかわかったものではない。良くて愛玩されるか、軟禁か。悪くすれば実験体。
どちらにせよ、ヒトの下位のモノとして飼われる事には変わりなかった。
しかし、発見したのならば、国やその保護機関へ届け出なければならないだろう。
来るか、と手を差し伸べると、茶の瞳が揺らぎ、色を濃くした。
(茶というより、琥珀だな)
切れあがった釣り目に戸惑いを感じ取って、更に続ける。
「来るか、来ないか」
選ばせることに意味がある。
もしも来ないと言われても、国には連れて行く心算だった。しかしその場合、二角がこの少年の身柄を保障するつもりはない。ノルトヴェステンの王の判断によって国で保護されるか、機関へ引き渡されるか。
しかし、少年はその細く白い手を伸ばしてきた。
(コレは俺を選んだ)
それが二角の元へと届かぬうちに、彼はキツネの手を取った。
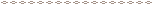
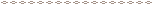
細い肢体を抱えあげると、驚くほど軽かった。
「見たくなければ目を瞑っていろ」と言い置き、所々荒らされ破壊された城内を歩く。その言葉に対し、ぐったりと力を失った尾が反応を返すことはなかった。
間もなく、陣営内の応急用に設えたテントへ到着した。硬い簡易ベッドの上に少年を下ろす。
(寝ていたのか)
何の事は無い。反応が無かったのは眠っていたからだ。しかし、見れば見る程に見事な毛並みをしている。腫れあがった顔が残念だ。きっと、とても美しい顔立ちをしているだろうに。
熱を持った頬をサラリと撫でると、二角は己の王を呼ぶ為、テントを後にした。
「やはりな……」
そう言って王は渋い顔をする。
かねてからの噂通り、ドゥエの国には甚振られた混合種がいた。それも、≪キツネ≫の。
「とりあえずはお前に預けよう。――ちゃんと面倒を看てやりなさい」
「は」
言われずともそのつもりだった。彼が己の手を取ったその瞬間に決めたのだ。この宝石はもう自分のモノだ――と。
「だがつまらぬな。オイシイところは全部お前が持って行ってしまって。私が来た意味がない」
囚われの姫を颯爽と助けるのは王の役割だろう、とよくわからない持論を語る。
「……だから申し上げたではありませんか。見届けるだけのことに陛下がいらっしゃることはないと」
呆れを含んだ溜息をまじえて言葉を返す。
天命を過ぎているにも関わらず、この王は無駄にフットワークが軽い。
今回もわざわざドゥエまで出向く必要など無かったのだ。それを、単に暇だったから、と周囲の反対を押し切り出てきてしまった。警護を任されているこちらの身にもなって欲しいものだ。
しかし、混合種や改良種といった区別を良しとしないノルトヴェステンの王が、本当は何を思ってドゥエまで来たのかは皆周知している。
そして、二角自身がキツネを発見してしまっている。王の懸念はこれだった。
「おお、目が覚めたか」
それにしても奇麗な少年だ。アーモンド形の気が強そうな釣り目はどこか嗜虐心をそそる、危うい色気を具えている。
ピクリと、僅かにミミを動かしただけで無反応な少年に対し、二角はお座成りに彼の仕える主の身分を教える。
「ノルトヴェステン王、クラウス=キースベルト陛下だ」
それに対しクラウスは「構わん、構わん」と軽く応え、腰を上げる。
「――では、青軍隊長ドノ、国へ帰るとするか。キツネの少年よ、ゆっくりと休まれるといい」
からかう様な口調はこの王の常だ。しかし、邪魔者はこれで消えた。
「名は」
「……アイ」
短く問うと、やや擦れた声で少年はその名を名乗った。
想像していたそれよりは僅かに低めだったが、ドゥエの王に嬲られた後だったのだろう、その声は色を唆るものだった。
(アイ、か)
存外、可愛らしい名だ。彼の名と引き換えに、二角は己の名を引き渡した。
「ロルフ=ライヒシュタインだ」
アイは、そのミミと尾を微かに動かした。何かを噛み締めているかのような様子だ。
(この子供は案外分かり易いな)
ロルフは心中で呟き、アイがこちらを見ていない隙に、僅かにその唇を緩めた。
To be continued.