桃色綿飴
▼Prologue
釦が“運命”に出会ったのは突然の事だった。
泣き叫んでいた釦は彼によって摘み上げられ、そして、知ったのだ。このひとが自分の“運命”だということを。
『お前の名前は“ちぃ”だ。千鳥、のちぃ』
“運命”がそう言った瞬間から、釦は千鳥になって、大嫌いな世界は大好きな世界へと一変した。
これは釦――千鳥が運命と出逢った話。小さな小さな恋のお話。
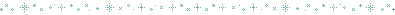
話は釦が千鳥になる、ほんの少しだけ前から始まる。
まだ釦という名だった小さな彼にとって、その日はとても大事な、大人になるための第一歩を踏み出す日だった。
ガーデンのものは皆、十五になって学校を卒業すると、一度は外の世界へ留学しなければならない。そして、一年後無事に帰還する事。それがここ、神の愛する庭、≪ガーデン≫においての決まりだ。
そうは言っても、殊更に危険があるというわけでもない。釦はそんな話を聞いた事は無かったし、大人たちもただ楽しんでこいとしか言わなかった。
『ガーデンにはガーデンの決まりがあるように、他の世界にもその世界の決まり事があるのです。律を犯してはいけません』
釦たち今年の卒業生がガーデンの門を潜り抜けるその瞬間まで、厳しい教師はそう繰り返していた。
その言葉を上の空で聞き流しながら、釦は灰色の瞳を星のようにキラキラと瞬かせ、まだ見ぬ世界へと思いを馳せていた。
やっと、やっと自分の番が訪れた。先輩たちの語るおとぎ話のような経験談を聞くだけの立場から、今度は自分がその主役へと変わるのだ。
それに――、釦はうっとりと夢想した。
もしかしたら、留学先に自分の“運命”がいるかもしれない。
釦はまだ、自分の“運命”と出逢っていなかった。
ガーデンの外の者や、余所からやって来た者、また、稀にではあるが≪監視員≫と恋に落ちる者もいる。だから、「もしかしたら」と。そう思う気持ちを抑えられなかった。
小さな心臓はドキドキと高鳴って、ワクワクしてたまらなかった。心はふわふわと、まるで彼の髪の毛のように弾んでいた。
そうして期待に膨らんだ胸を抱え、釦はガーデンから足を踏み出したはずだった。
▼01
(なのに、ひどい……)
蔦の絡む大きなゲートをくぐり、雲のように濃い霧の中をずっと歩き続けて、夢にまで見た新しい世界にたどり着いたのにもかかわらず、釦の気持ちは萎みきっていた。
その世界は異世界からの来訪者に対し、とても冷たかった。
薄いシルバーグレイの瞳に映ったのは、先輩たちの語っていたような深い緑の森でも、紅く美しい砂漠でもなく、ただただ、灰色ばかり。まだ日は高いのに、見上げた空は狭く、暗い。空気は鼻を刺すし、喉もとても痛い。
汚れきったその世界をいくら歩けども、きれいな泉や森、ましてや実のなる木なんて、到底見つけられなかった。
先輩たちは『食べるものさえ見つけられれば、後は大丈夫』と、そう言っていたのに。
どうして自分だけがこんな冷たい所にたどり着いてしまったのだろう。この世界はひどく意地悪で、とても生活なんて出来そうもない。
ここは留学先だ。この世界は釦を育んだ、優しく温かなガーデンではないのだ。
頭で理解はしていても、感情は納得してくれなかった。
どうして、何で自分だけ。こんなのって聞いてない。
突き付けられた厳しい現実に、釦は泣いてしまいそうだった。
まだ一日も経っていないというのに、もうすでにガーデンが恋しい。見送ってくれた白と黒の先輩たちを懐かしく思う。
『お前は小さな猫だから……誰か他の者も一緒だといいのだが。そうでなければ、油断をしてはならないぞ』
大きな黒豹と白虎の彼らはいつもケンカばかりしていたが、二人して同じ世界に渡り、一年を過ごしたと言っていた。
せめて自分にもパートナーがいたらよかったのに。どうして、何で。
誰にともつかない抗議を繰り返しても、かたわらで答えてくれる者はいない。灰色の世界で、釦は独りきりだった。
ここに生きるものたちは、生まれて初めてガーデンを出た釦にとって、とても恐ろしかった。
ひとの姿で生きるものたちも、獣の姿で生きるものたちも、ガーデンで生きる仲間とは様子が違っているのだ。その上、ひとは釦を見つけると「モモ!」だの「ピンク!」だのと叫び、追いかけて捕まえようとさえする。
恐ろしい早さで駆ける四角いかたまりも見た。初めて目にするそれが何かを食べるようには思えなかったが、小さな猫である釦にとって、立派な外敵であることには違いなかった。
『安易にひと型になってはいけません』
教師の言葉が頭の中に響く。
安心できる場所を見つけるまで、その世界の律を知るまで。姿を変えてはいけません。
猫の姿でもひとの姿でも、この世界が生き辛いところであることは変わりない。ただ、姿を隠すには小さな方が便利だった。そのため釦は小さな猫のまま、温度を感じさせない、硬い建造物の街を彷徨っていた。
こんなはずではなかった。留学というのは、もっと楽しくて明るい、新しい経験をたくさんするためのもの。そうじゃなかったのか。
どうして、何で、こんな苦しい思いをしなければならないのだろう。
(こんな世界、大嫌い)
もう泣く事も出来ないほど、釦は疲れていた。
お腹はぺこぺこで小さな体はふらふらするし、ひとや鳥に追われ、あちこちを逃げ回った脚はガクガクと震える。だが、喉を潤す事も、空腹を訴える腹の虫を宥めることもままならなかった。
油の浮いた水たまりに、腐った食物。それを変化させるような大きな魔法など使えない。
それでも何とか――そう思って何度となく魔法をかけてはみたものの、やはり、釦の小さな魔法では叶う事は無く、ただ疲労が増しただけだった。
(もう、だめ。限界……)
新しい世界へ来て二日目。
釦はたくさんの灰色に紛れて、それでも必死で生きている小さな緑の陰に隠れていた。そして、その場でうずくまったまま、一歩も動けなくなってしまったのだった。
Continued.