桃色綿飴
釦が新しい世界に失望してしまった、その日の深夜の事。
男はとてもいい気分で浮かれていた。大きな商談はうまくまとまったし、一人で祝杯を挙げに入った店も大当たり。
三十路も近くなると、出会いを求めた若者で溢れるクラブやバーは居心地が悪い。かといって、ごく一般の者が出入りする場も遠慮したかった。
“普通”を装うための仮面を外し、息を吐ける場所。そこはまるで熊の様な、およそ男にしか見えないママが経営する、こぢんまりとした隠れ家だった。
そこで美味い酒を飲み、アルコールは男の気持ちを高揚させていた。
そうしてフラフラと家路についていたのだが、マンションの生け垣にうずくまる小さな生き物を発見してしまった。
初めは風に飛ばされた洗濯物かと思ったのだが、かがんで見てみると、そこにあったのは雑巾やタオルなどではなく、小さな猫。それも、桃色の。薄汚れてはいるが、猫の長毛は自然には見られない色をしていた。
夜店の綿菓子。もしくは子供の気を引くために色付けされたひよこ。薄桃色のふわふわは、そのどちらかにしか見えない。大方、どこかで悪戯でもされたのだろう。
男は猫をひょいと摘み上げた。それでも猫は目を覚まそうとしない。警戒心が薄いのか、それともどこか具合が悪いのか。
泥で汚れた毛玉を慈しむように抱え、男はそっと呟いた。
今日は良い日だったから――。
「お前にも、お裾分け」
微笑んでそう囁き、男は猫を自宅へと連れ帰った。
▼02
――ちぃ
チィチィ。チィチィチィチィチィチィ!
チィチィと囀る鳥の声に、男は目を覚ました。
今までこんなに煩く囀る鳥はこのあたりにいなかったはず。休日のこの日に限って何事だ。
無意識の内に窓を空けてしまったのかと思い、うぅ、と軽くうめき声を上げながら、だるい体を引き摺るようにして男はベッドを下りた。
そして、そこにピンクの毛玉を発見する。昨夜彼が拾った猫だ。
チィチィとかしましいその鳴き声はどうやら外の鳥ではない。そこの毛玉だ。窓はきちんと閉まっているし、音を発するようなものはこの猫以外にいない。
なぜ、猫が囀るのだ。ミィと鳴くのならまだ分かる。だが、この桃色はニャンでも、ミャーでもなく、チィチィと囀っている。チュンとも、ピィとも違っているが、その声はどう聞いても鳥のさえずり。
やはり、屋台のひよことしか思えなかった。
男は綿のかたまりの様な猫を拾い上げ、思う。
綿飴みたいな桃色で、その上鳴き声は小鳥。不思議な生物もいたものだ。科学が発展した現代においても、まだまだ謎は残っていたらしい。
「お前、ミィとかニャーとか、他に鳴き方あるだろ」
ブルブルと震えて泣き続ける猫を上から見下ろし、僅かに溜息を零した。
昨夜、酔っぱらってお持ち帰りしてしまったのは自分だ。人に譲るにしろ、自分が面倒をみるにしろ、とりあえず名前を付けてやろう。それに、おそらくこの猫は他人に譲ってしまうことはできない。なにしろ不思議生物なのだ。
「名前、何がいい? ひよこ、綿飴、それともモモか?」
返事は無いと分かっていて聞く。すると、猫はそのどれも嫌だというように、よりかしましく鳴いた。
「そううるさく抗議するなよ。……チィチィ鳴くから、お前は“ちぃ”だ。千鳥で、ちぃ」
猫なのに、鳥。少し的外れだが、猫には一番似合っているように思った。
「それに、俺が千裕だからな。揃いでいいだろ?」
千裕はそう言って、千鳥と名付けられた桃色に笑いかけた。
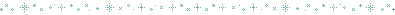
(運命、だ……!)
目が覚めたら知らない所へ来ていた小さな猫が、その体を持ち上げられた先に見たもの。それは釦の“運命”。優しそうな男は困ったような顔をして、泣き叫んでいた釦を見つめている。
釦の頭では鐘の音が鳴り響いていた。薄汚れたスモークで覆われていた世界が晴れていく。刺々しく、まるで異物を排除するかのように釦を苛めていた世界が、突然、優しく柔らかいものになったのだ。
(僕の名前は釦だよ!)
彼はひよこだの、綿飴だの、そしてよりにもよって、自分を追いかけ回したひとのようにモモだなどと、名前を付けようとしている。
必死で名前を告げたのに、彼は分かってはくれない。そしてはた、と思い出した。この世界のひとは、ひと以外と言葉を交わせないのだ。
優しくなったはずの新しい世界が、柔らかい心をほんの少し、チクリと刺す。しかし次の瞬間、運命が告げた言葉によってそんな小さな痛みは跡形もなく吹き飛んでしまった。
「お前は“ちぃ”だ。千鳥で、ちぃ。俺の千裕と揃いでいいだろ?」
この時から、小さな桃色の猫の名は、釦から千鳥になった。
(あぁ、どうしよう)
釦は――千鳥は嘆息した。
“運命”から、千裕から名前を貰ってしまった。ガーデンで生まれたものにとって、名前と言うものはとても大切なものだ。何よりも重く、そして柔らかく、形のない宝物。だから、“運命”を見つけたものは相手にそれを贈るのだ。
甘く、柔らかな綿の様な、相手を縛る鎖。それが名前だ。
(チヒロ、彼はチヒロ)
千鳥の“運命”は千裕と名乗った。そして、お揃いだ、と。そう言って笑ったのだ。
お揃い。同じ。二人で一緒。その言葉はほの甘い響きをもって千鳥を魅了する。
(そして、僕の名前は千鳥。今日から、千鳥だ!)
千裕の腕に抱かれ、千鳥の心はピンク一色に染まり、ふわふわと柔らかなもので満たされていた。まるで彼自身のように。
Continued.