Misfortune
▼第参話 カミサマの趣味
「ゆきちゃん。お昼やでぇ」
不貞寝を決め込んでいたら、いつの間にか昼時になっていたらしい。御簾の外から声がかけられた。
「ここで食べはるやろ? 移動するのつらいでっしゃろ」
「死んだのに、飯?」
全身打撲に続き、ご飯まであるのか。死後の世界もなかなか現実的だ。
「ゆきちゃん、お腹すいてはるやろ?」
「そういえば空いてるな。なぜか」
普通、死んだらそういう欲求はなくなるのではないかとも思うのだが、確かに腹が減っていた。
ファミレスで不味いコーヒーを飲んだのと、先程の白湯くらいしか口にしていないのだから、腹も減るはずだ。ただし、生きているなら。
「せやろ? ほな、一緒に食べよな。ゆきちゃんのは雑炊作ったんやで。あーんってのん、させとくれやす」
「いらん。自分で食べる。ていうかカミサマも食べるのか?」
「そら食べるに決まっとるやないの。食べへんでもすぐに餓死するとか、そういうこっちゃあらへんし、毎日三食は食べへんでもええんやけどな。ボクの場合はもう、趣味やなぁ。現世(うつしよ)は美味しいもんがいっぱいあって、ほんまええよなぁ」
「へぇ、そんなもんなの……」
このカミサマは食事が趣味だと。カミサマも食事を摂るのなら、死人の俺が空腹なのも当たり前なのだろう。
そんなことを考えながら、1人用の小さい土鍋の蓋を取ると、そこにあったのは予想していた卵雑炊ではなく。
「こっ、これっ、蟹! 蟹雑炊! カニカマじゃないよな!?」
蟹! 匂いからして出汁も蟹っぽいし、最高だ。
「ゆきちゃん、蟹好きなん? ほなよかったわぁ、ほんまもんやで? ほら、ふぅふぅしたる」
入社してすぐに不景気の煽りをくらってボーナスカット、そのまま業績は落ちて給料は上がる気配もなかった。その上、最近は入院していたため給料も少なく、貧しい食生活を送っていた。
特に、仕事の繁忙期ともなるとカロリーさえ摂取できればそれでよし、といった生活だったのだ。きっとこれは俺へのご褒美に違いない。あぁ、蟹なんて何年振りだろう。
「かっ、神様! ありがとう!」
あぁ、これでこそ天国、極楽。
働きだしたらボーナスで死ぬほど美味いものを食うという夢は叶わずじまいで死んでしまったが、この分だと食には不自由しなさそうだ。食事が趣味のカミサマに感謝だ。カミサマの後ろに後光が見える。
さぁ、スプーンはどこだ、と勢い込んでいると、それはすでにカミサマの手に握られていて、その上湯気の立つ雑炊を冷ますように息を吹きかけている。
これでもし、俺が女の子だったら一発KOで落ちただろう。美形は何をやっても様になる。
さっきは興奮してスルーしてしまったが、これはやはり、『ふうふう』とやらをしているのだろう。なぜすぐに拒否を示さなかった、俺の阿呆。
「ほら、あーんや、ゆきちゃん、あーん」
「いや、自分で食えるし。いいってば、さっきも断っただろ」
「ふぅふぅとあーんはセットやで、ゆきちゃん」
ほら、ほら。
奇麗な、と言うには少し子供っぽい、期待に満ちた笑顔で匙を口元へ近づけた。
「く、くそぅ……」
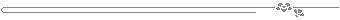
おいしそうな匂いに鳴く腹の虫に負け、結局、カミサマの手ずから食べさせられてしまった。
甚だ不本意である。
「ごちそうさん」
「よろしゅうおあがりやす」
カミサマは完食した俺を嬉しそうに眺めて、丁寧に言葉を返す。カミサマの言葉遣いは少々古臭い。だが、その見た目によく似合っている。
営業ではただただ威圧感しか感じなかった西の訛りが、こんなに柔らかな響きを持っていることに今まで気付きもしなかった。俺の精神はいつもギリギリで、そんなことを感じる余裕はなかったのだ。
――あぁ、俺、疲れてたのか……。
「ゆきちゃん、夜はおうどんでええ?」
「え、もう俺、普通に食えると思うんだけど」
「ほんなら、甘いもんもつけたるから」
カミサマは笑顔のくせに押しが強くてマイペースで馴れ馴れしい奴だが、美味いものは食べさせてもらえるし、案外、いい奴かもしれない――すっかり、カミサマに餌付けされている俺であった。
![]() 続
続 ![]()
ゆきちゃんは食欲に忠実。