Misfortune
▼第漆話 慰撫
いつの間にか、俺は桜の木になったらしい。
松月の瞳よりもやや暗い、しかし黒や茶にはけして見えない黄緑の瞳。自分のものであるとは到底思えないそれが、俺に現実を教える。
『お前は既に死んでいる』
懐かしのアニメヒーローの決め台詞のような言葉が頭に浮かんだ。
今まであまりにも普通に食事をしたり、痛みを感じたりしていたため、死んだという気がしていなかったのだ。
ここでの生活は変わった夢を見ているようで、死んだと言われてもどこか他人事のように捉えていた。
それが、瞳の色が変わるという現実的にありえない状況に陥って初めて、自分の死を実感した。自分はもう生きていないという事実が、急に現実味を帯びて俺に迫ってくる。
――もう、生きて家族には会えないんだな……。
そう思うと目の奥が熱くなってくる。狼狽も驚愕も通り越し、唯ぼんやりと過去を思った。
――短い一生だったなあ……。
学生時代は部活に打ち込み、大学に入って酒と女を覚え、社会に出てからは精神をガリガリ削られながら働いた。
特にこれといった特徴も無いけれど、それでも俺にとっては大事な25年間だった。ここ数年は友人とも疎遠になり、何のために働いているのかもよくわからないような生活だったとしても。
「ゆきちゃん……」
いつの間にか隣に来ていた松月が、小さく擦れた声で俺を呼ぶ。
ひと言でも声を発したら、張りつめていたものが零れてしまいそうで、視線だけを松月へ向けた。
松月は細い眉を寄せ目尻を赤くして、どこか痛いような、辛いような、悲しい、ような。そんな表情で俺を見ていた。
今にも涙を流しそうな潤んだ双眸を見て、耐えていたものが堰を切って溢れだす。
塩辛く熱い体液がボロボロと零れ落ちる。もうずっと流していなかった涙が頬を伝い、久しぶりの感触に驚いた。
――あぁ、せっかく我慢していたのに。メソメソと落ち込むのは嫌いなのに。目の奥も頭も痛くなるに違いない。鼻だって詰まってしまう。
高級そうな着物の袖でそっと頬を拭われた。笑みを浮かべていない切れ長の釣り目は、ややもすれば冷たく感じる。松月はその美しい瞳に悲しみを湛えてじっと俺を見つめ、そのままゆっくりと、整った顔を近づけた。
目尻や頬、額に薄い唇の感触が残る。
桜の花びらが落ちるような軽さで、唇に接吻を落とされた。
どちらも何も言わず、しんと静まり返ったなかで、松月の手は泣き続けるおれの頭を撫でていた。
まるで子供をあやすように。よしよし、と。
涙の膜を通した視界は歪みまくっていて、松月に手を引かれて邸へと戻った。
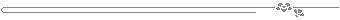
俺に宛がわれている部屋へと戻ってもまだ、俺はメソメソと愚図り続けていた。
溜めこんでいた涙はいつになったら枯れるのだろう。こんなに泣いて、体中の水分が足りなくなったらどうするのだ。カラカラに干からびてしまうのではないか――そう思ってしまうくらい、壊れた涙腺は涙を流し続ける。
その間も、松月はずっと俺をあやしていた。
松月は言葉ではなく、肌に感じる態度で慰撫する。頭を撫で、髪を梳き、あちこちに口づけを落として。
他人の体温というのは温かく、そして安心できるものなのだと知った。
いや、これまでの人生でも知っていたつもりだった。しかしそれは慰める側としての知識で、実際に体感するのは初めてだった。
当たり障りのない人付き合いを繰り返していた俺は、たとえ心が折れそうなほど落ち込んでも、他人に慰められることなどなかった。
泣きわめく子供を宥めるのが大人、泣いている女を慰めるのが男――そんな固定観念でガチガチに固まっていて、他人に頼ることは恥で、大人として情けないことだと思っていた。
――もう死んでるんだから、仕方がない。
他人に弱みを見せることなど死んでも出来ないと思っていた、ほんの数日前の自分に言い訳をする。
もう、泣いてもいいのだ。それに、松月はカミサマで、人間は皆、神様を頼るものではないか。
「ゆっくりおやすみ、ゆきちゃん……」
どうでもいい事を考えられるだけの余裕が生まれたころ、そう耳元で囁かれた。
大人になってからの落涙は非常に体力を消耗する。松月の手になだめられるまま、俺はゆるゆると眠りへと落ちていった。
![]() 続
続 ![]()
ゆきちゃんの子供返り。松月はあやし上手。