Misfortune
▼第捌話 霞か雲か
「ゆきちゃん、じゃあ、ほんまは行きたないねんけど……ゆきちゃんが言うならしゃあないし……。ほな、ちょっと行ってきます」
「おぉ、仕事しろ。そんでなんか土産に美味いもの買って来い」
松月の前で泣きまくった挙句、子供のようにあやされた――恥ずかしい記憶が脳内の片隅から出てこないうちに、外での仕事があると言っていた松月を追い出した。
俺の読み通り、初めのうち松月は行くのを相当渋っていて、まるで子供のように『いやや、いやや。ゆきちゃんとおりたい!』なんて騒いでいた。
大人として働くことは云々から日本人にとっての神頼みの重要性までを訥々と語り聞かせてやり、宥めて叱って、登校拒否の子を持つ親の気持ちが分かりかけたところでようやく、松月は腰を上げて出かけて行った。
その様はいかにも渋々といった体で、途中で抜けてくるのではないかと少々危惧している。だがまぁ、他人、というかカミサマ仲間の目もあることだし、大丈夫だと信じたいところだ。
そうやって、昨日のことなどまるで無かったかのように接してくれる松月にはありがたさを感じていたが、それを言って自分から蒸し返したくはない。
もしかすると、わざとああいった態度をとってくれたのかもしれない。それにしてもダダをこね過ぎだったが。カミサマとしてあの言動はどうなのか。祀られている存在なのだから、それなりの態度というものをとるべきではないのか。
ひと悶着の後やっとこさ落ち着いて緑茶を啜り、俺はそのような事を考えていた。
――あぁ、うまい。やっぱり日本人には緑茶だ。あと、できれば羊羹が欲しい。栗入りだと尚良し。 ……おやつに寄越せと強請ってみるか。
ふと、この屋敷で一人きりになるのは初めてだということに気付いた。
松月がいないのだから、今日は三時のおやつタイムもない。生きていた頃はもうずっと一人暮らしだったにも関わらず、広すぎる屋敷は俺に寂しさを感じさせた。
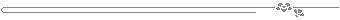
その後、緑茶に含まれるカフェインの作用で尿意を催し、小用を足しに 行った。
そして、俺はとんでもないモノを目撃してしまった。ソレを見たのは、広い屋敷の端にあるトイレを出て、俺に与えられた一室に戻る道すがら。
白くて、ぼやぼやぁっとしていて、足が無い。向こう側が透けて見えるソレ。壁の中に消えて行ける、実体を持たないソレ。
「うわああああ!! お化けだ! 幽霊だ! ゴーストだ!! つかなんだよ!! 俺は霊感なんて無いぞ! 絶対! もしも、もしも有ったとしても、だ! 俺は認めない! 断じて認めない!!」
学生時代の部活で鍛えた声で、腹の底から恐怖の叫び声を上げた。
「ただいまぁ、って、え? ゆきちゃん?」
声を上げたちょうどその時に松月は帰宅したらしい。
何を想像したのか、「変態さんでも来はったん!?」と斜め上の発言をしながら俺の許へ現れた。
助かった! とばかりに駆け寄って奴の着物の袂をギュッと掴む。
「しょ、しょ、松月! お化け! 幽霊!! つかなんで神社に!? 寺に行けよ!! そんで念仏でもなんでもあげてもらってさっさと成仏しろ!!」
自分のことは棚に上げ、俺はたった今遭遇した心霊現象を訴えた。
すると、松月は何かに思い当たったらしい。あぁ、あれか、という様な顔をした。
「あれは霞やで。ちょっと屋敷を片してもらってたんやけど、驚かしてしもたなぁ」
「霞!? なんだそれ! あの幽霊の名前か!?」
「霞は霞や、ぼんやりしたもん、ちゅうことやな。ボクの眷属や」
そういえばこいつカミサマだった。桜だった。
「まだ紹介してへんかったなぁ」、なんて暢気なことを言っている和風美人はカミサマなんだ。そりゃあ、眷属の一つや二つ、いらっしゃることでしょうよ。
「はぁ? 俺は一人だったんだぞ? そんな時にそんなモノ寄越すなよな! 掃除するなら掃除するで、俺に頼むかさっさと帰って来るかしろよ! このドアホが!!」
俺は恐怖が過ぎると怒りに変わるタイプだったらしい。
理性は震えあがって飛んでいき、混乱した脳ミソでは、いつものように『カミサマだから仕方ない』、と納得出来なかった。恐怖というものはそう簡単に拭い去れるものではないのだ。
微妙に被っていた猫も放り投げんばかりに脱ぎ捨て、俺をそんな目に遭わせた原因である松月に詰め寄って怒鳴り散らした。
「ゆきちゃんは怖がりさんやったんやなぁ」
「何とでも言え! 怖いもんは怖いんだよ!!」
「まぁまぁ、今日はもうずぅっと一緒に居たるし、夜も一緒に寝たるから。な?」
宥めるように言われたそれは、確かに、今の俺にはありがたい提案ではあった。
だが、それは25歳の日本男児のする事としてはかなり恥ずかしいのではないか。たとえ俺が男として少し情けないくらい、非常に怖がりだったとしても、だ。
「で、でも、霞はお化けじゃないんだろ? な?」
昨日、粉々に砕け散ったと思っていたのだが、大人としてのプライドはまだ残っていたらしい。それが素直に頷いてしまうことを拒否していた。
そのため、頼むから「そうだ」と言って、「幽霊などいない」と、松月には断言して欲しかった。
一人きりは恐ろしいが、大のオトナが、それも男女ならいざ知れず、男同士が二人並んで寝るという恥ずかしさもまた、恐怖と同じくらい大きい。
そうして羞恥心が湧くと共に、何処かへ行っていた平常心が僅かに戻ってきて、俺は現在の状況に気付いた。
昨日と同じように松月に抱きついている。いや、自分からしがみ付いている分、昨日よりも激しく密着している。 取り戻しかけていた理性が再び逃亡しようとした。
身体を離そうとした俺に対し、松月は恐ろしい言葉を放った。
「霞は幽霊とちゃうけどなぁ。他のはどうやろなぁ。あぁ、霞はちゃうんやけどな、霞は」
「ほ、他の!? 他のがいんのかよ! つかやっぱりお化けもいるのかよ!!」
「さぁ、いるかもわからんし、おらへんかもしれんし……」
「わ、わかった、わかった!」
嫌らしいくらい“霞は”、と繰り返しては恐怖を煽る。
先程見たモノはまだ網膜に焼き付いており、離れてくれる気配は皆無だ。せっかく離した手が、再び松月の着物へと戻ってしまう。
――こいつにはもう泣いてる所も見られたんだ、今更だ!
恥も外聞もかなぐり捨て、俺は松月の申し出を受けたのだった。
![]() 続
続 ![]()
ゆきちゃんの子供返りは続く。